 |
| 弊社代表の最新刊 『生物多様性と倫理、社会 ―改訂版―』(法律情報出版)が刊行されました。 | |
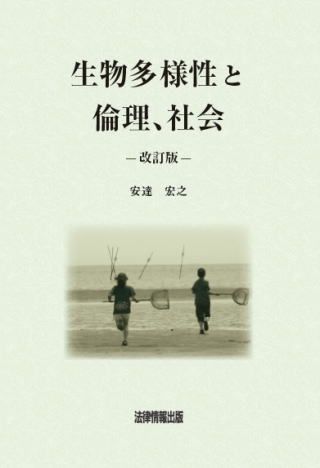 |
|
| 安達宏之 著 〇 『生物多様性と倫理、社会 ―改訂版―』 〇 法律情報出版 2023年3月刊行 〇 生物多様性がなぜ大切か。 そこに、にぎやかな生きものの世界さえあれば、 子どもたちにはわかりきったことなのかもしれない。 〇 第1章 「生物多様性」とは何か 第2章 企業と環境 第3章 企業と生物多様性 第4章 海の生物多様性と倫理、社会① ―東京湾三番瀬の自然と開発 第5章 海の生物多様性と倫理、社会② ―自然再生と市民参加の課題 第6章 人と生物多様性① ―生命倫理、環境倫理を考える 第7章 人と生物多様性② ―人にとって保全すべき生物多様性とは 第8章 法と生物多様性① ―人権と「自然の権利」 第9章 法と生物多様性② ―環境法の進展と課題 � 〇 定価:本体1,600円 (+税) 〇 全国の書店で発売中(書店でお申し込みできます) ISBN978-4-939156-47-2 出版社(法律情報出版)にて直接申し込むこともできます 〇 問い合わせ・申し込み先 法律情報出版 <お問合せ・お申し込み> Fax: 03-3367-1361 E-mail: office@legal-info.co.jp 〇 |
| 本書「はじめに」より― 「生物多様性」という用語は、自然環境の保全を考える際に必ず登場するものです。しかし、古くから使われている用語ではありません。1992年の地球サミット(国連環境開発会議)やその年に採択された生物多様性条約によって、世界中に一気に広まった用語であり、その歴史はわずか30年程度のものです。 そうした事情も影響しているのか、「生物多様性」について語られることが多いとはいえ、その意味を正確に理解できている人は決して多くはないようで す。 本書では、こうした生物多様性の意味や意義について考えていきます。生命が誕生して40億年の中で、現在は、6 回目の大量絶滅時代と言われています。それを引き起こしているのは、私たち人類です。この危機の深刻さを認識するためにも、生物多様性への正しい理解が求められています。 本書では書名の通り、「生物多様性と倫理、社会」をテーマとしています。生物多様性そのものの解説にとどまらず、「生物多様性」に関する「倫理」や「社会」のあり方について考えていきます。 そもそも「生物多様性」を考える上で、生命に関する難しい問題も横たわっています。例えば、「人と他の生物の区別はつくか?」という問いに、説得力 のある答えを出すことはできるでしょうか。 また、保全すべき対象である「自然」とはどのようなものでしょうか。人が立ち入ることがない原生自然のみが保全の対象なのでしょうか。あるいは、田 園風景が広がる里山や近所の公園の森なども対象に加えるべきなのでしょうか。 こうした根源的な問いについても、現実の法や政策の経緯と現状も踏まえつつ、本書では正面から考えていきます。 本書の特色としては、「生物多様性と倫理、社会」を考える上で、「企業」と「NPO」の2 つの視点から論じていることが挙げられます。 なぜ、「企業」と「NPO」なのか。これは、一義的には、極めて単純な話として、筆者がこれまで深くかかわってきたアクター(主体)が企業とNPO(特 定非営利活動法人という狭い意味ではなく、広く市民活動・市民運動を行うグループという広い意味で使います)であったからです。 ただし、それだけの理由によりこの2 つの視点から論じるわけではありません。生物多様性の保全(あるいはその逆の自然破壊)に関係するアクターとして、この両者は、良きにつけ悪しきにつけ、極めて重要な役割を果たしています。そうしたアクターやそれを取り巻く状況を探求することにより、具体的な 生物多様性の保全のあり方を描くことができると考えたからにほかなりません。 筆者は、特に海辺の生きものが大好きです。本書は生物多様性の危機や政策の課題について多くのページを割いていますが、そうした課題を提示する意識の根底には、対象となる自然が好きだという気持ちがあります。失うにはあまりにもったいない、人にとって大切なものだと思うからです。 本書を読みながら、対象となる自然に思いを馳せ、自然や生きものについて興味をもち、それを好きになってくれる人が増え、ともにその抱える課題につ いて考えていけることを願ってやみません。 ようこそ、にぎやかで楽しい生物多様性の世界へ。 |
||
| 2020年3 月 早春の干潟を歩いた後に 安達 宏之 |
||
| 改訂版の発行に当たって 改訂版では、気候危機や海洋プラスチックなど、急激に変化する生物多様性を巡る動向を反映させました。また、本書を使用した講義では、毎回学生たちに問題を投げかけ、すこしでも議論できるような場を設けるように努めています。そうした議論の中で得られた知見もできる限り本書に反映させました。改訂版の立役者は学生のみなさんです。ありがとうございました。 |
||
| 2023年3 月 変わることなく、今年も早春の干潟を歩いた後に 安達 宏之 |
||
| 目次 CONTENTS はじめに/改訂版の発行に当たって 第1 章 「生物多様性」とは何か 1 「生物多様性」とは 2 自然にふれながら生きるということ 3 生物多様性の重要性 4 生物多様性の危機 第2 章 企業と環境 1 企業はどのような存在か~ “負の歴史”から考える 2 企業と環境経営 3 SDGsと企業 第3 章 企業と生物多様性 1 なぜ、企業は生物多様性保全に取り組むべきなのか 2 事業者の基本的な考え方と取組み方法 3 生物多様性保全に向けた企業の取組み 第4 章 海の生物多様性と倫理、社会① ―東京湾三番瀬の自然と開発 41 1 干潟・浅瀬の役割 2 三番瀬とは 3 日本の海辺の開発 4 三番瀬埋立問題 第5 章 海の生物多様性と倫理、社会② ―自然再生と市民参加 1 自然再生の動き 2 三番瀬埋立計画の白紙撤回と「三番瀬円卓会議」 3 かつての海辺の聞き取り調査とアマモ場再生 4 小さな地域で小さな取組みを増やす 5 NPO・市民活動・市民運動とは 第6 章 人と生物多様性① ―生命倫理、環境倫理を考える 1 生命とは何か ~動的平衡論をヒントに考える 2 人は他の生物と区分できるか 3 環境倫理学への接近 第7 章 人と生物多様性② ―人にとって保全すべき生物多様性とは 1 保全すべき生物多様性とは何か 2 生物多様性をどのように保全するか 3 生物多様性の重要性をどのように伝えるべきか 第8 章 法と生物多様性① ―人権と「自然の権利」 1 「人権」とは何か 2 自然に権利はあるか 3 「人権」から自然を考える 第9 章 法と生物多様性② ―環境法の進展と課題 1 地球環境保全と国際法 2 生物多様性条約とABS 3 日本における環境法の進展と生物多様性 4 環境権の行方 おわりに |
Copyright (C) Rakushisha Co.,Ltd. All Rights Reserved.